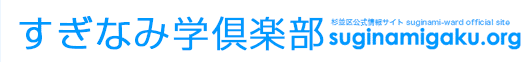小川未明さん
日本近代童話の父と呼ばれる
小川未明氏は「童話」について、以下のように述べている。
「自由の世界-創造の世界-神秘の世界-これが即ち童話であります。」
「永遠に対する憧れと、はかない、しかし常に若やかな美と、 この生活の尉藉を、私は、自ずから童話の世界に於いて求めるより他に途のないことを思います。」
「私等が、何等かの幻想や、連想によって、既に少年の時代に失はれた世界をもう一度取り返すことが出来たらどんなにか仕合わせでありませう。」
「もし其れによって、更に少年を楽しませることが出来たら、どんなに私たちは、芸術の誇りを感ずるでありませう。」
これらの言葉から彼の童話は人生の哲学に基づき、「直感が冴え」た「子供」のためのみならず、「永遠への憧れ」や「失われた少年時代の世界」を再び取り返したいと望む「大人」に向けて書かれたものであるということがわかる。
自らの思想と情熱により、独特の感性に基づいた美の世界を構築し「童話」という形を借りて、心の引き出しに仕舞い込んでいる「幼心」に語りかけて来る。
それゆえに彼の作品は、幼い頃、枕元に置いて何度もそっと開けては覗く宝箱の瑠璃玉のように、いつまでも輝きを失わないのではないだろうか。
『赤い蝋燭(ろうそく)と人魚』のルーツ 故郷上越市へ
小川未明氏は、48才の時(1930年)に家族とともに東高円寺に移り住み晩年を過ごした。最期の時もここで迎えるのだが、ここで過ごした時代は、すでに創作活動も中盤を越えた頃であった。
代表作の一つ『赤い蝋燭と人魚』は、1921年に執筆されさまざまな作家の挿絵で発行されているが、なかでも故いわさきちひろさんの絶筆でもある絵本は名高い。
「人魚」といえば、アンデルセンの童話『人魚姫』があまりにも有名だが、日本で「人魚」が登場する童話は稀だ。 そのルーツを彼の故郷、上越市直江津に訪ねた。
『赤い蝋燭と人魚』の銅像は、日本海の浜辺を見渡す高台の「船見公園」にある。 潮風をまとう浜辺に座って、船の安全を祈るかのごとく蝋燭を両手に持ち、海を眺める人魚。素朴で凛とした少女の眼差しは、さみしげだがどこか気品を感じさせる。
『赤い蝋燭と人魚』は、未明の幼児期の体験に根ざして描かれたと言われている。 生まれてすぐに、この地方の因習によって隣家の丸山家に里子に出された。この丸山家の家業が蝋燭作りであったという。
また、父・澄晴が建立に奔走した春日山神社を訪ねた。 小さな山の上に続く苔むした小さな石段を上がると、お宮の前に未明の碑がひっそりと佇んでいた。父の神社建立後、未明氏はこの春日山で家族と共に暮らし、山を歩いては自然石を集め、一人で空想に耽るのを好んだという。
『赤い蝋燭と人魚』の物語は、蝋燭づくりを商いにする老夫婦が、海の近くに建つ、山の上のお宮にお参りした帰りに、その麓に置き去りにされた人魚の娘を見つけ家に連れて帰るところから始まる。
美しくも恐ろしい北の海。海辺を見下ろす神社の麓の小さなまちを舞台に、やがて異形の娘が、私利私欲に目が眩んだ大人たちに翻弄されていく。 その哀しく、残酷な結末の物語には、やはり彼の幼少時の経験が、大きく影響を与えたようである。
「日本のアンデルセン」と呼ばれて
「日本のアンデルセン」と呼ばれる所以は、単純にこの代表作が人魚をモチーフにしたことだけではない。
ある時期から未明は「童話作家専従」を宣言し、いわゆるメルヘンという手法を用いて、雑誌や新聞に子供のための物語を一千編近く創作したという事実からも彼が日本の児童文学史上、アンデルセン的な役割を果たしていると言える。
しかし、アンデルセンと小川未明氏の大きな違いは、アンデルセンが現在に至るまで批評家や読者から賞讃を受ける一方、未明は常に絶賛と批判の両極端に立たされた作家である、という点だろう。
両極端の評価は『赤い蝋燭と人魚』に集中し、そこから彼の作品全体に及んだ。
そのためか熱狂的なファンからは根強く支持されているものの国を代表する童話作家として、アンデルセンのように名高い作家と比べると、日本の児童文学界においてその扱いは不遇であり「知る人ぞ知る」存在となりつつある。
しかしながら、『赤い蝋燭と人魚』は誰にどのような評価を受けようと、唯一無二の感動を世に与え続け、いわさきちひろさんを代表とする絵本作家たちに愛され、幾度となくモチーフとして描かれ絵本として出版され続けている名作である。
大自然の深淵な美しさと怖さ、小さな異形の者への思いやりや命の尊厳、人間の利己的なの欲深さ、経済優先の原理に目が眩む愚かさなどを鮮烈に、また象徴的に「童話」という伝わりやすい手法を用いて描かれている。
現在、多種多様な童話が書店に並んでいる中、未明氏の作品は決して色褪せることはない。 むしろ、今こそ彼の作品が再評価されるべき時期が来たのではないだろうか。
世に出て名を売るというような俗世のことに関心がなく、見えざるもの言葉なき小さき弱き者の代弁者として、魂の結晶のような詩でも小説でもない、一つのジャンルとしての『童話』を確立しようとした小川未明氏。
丸ノ内線東高円寺駅そばにある晩年を過ごした家を取り壊す直前に訪ね、ご家族に貴重なお話を伺った。
人間 小川未明
自然や路傍の石ころにも、魂や精神性を感じる未明の居宅らしく、広い縁側に面した庭には、石の灯篭、水鉢、岩や自然石を配し、中央には小さな池が二つ。 豊かな緑の繁る、落ち着いた佇まいが、来客者の目を愉しませる。
玄関から書斎まで、ツヤツヤと使い込まれた手触りの木の手すりが続き、足が悪かったという未明へのご家族の深い配慮も感じられた。 縁側の一番奥のすっかり片付けられた未明の元書斎にて、お孫さんにあたる小川英晴さんからお話を伺った。
生活は決して楽ではなかったが、この杉並の家では家族とともに晩年を穏やかに過ごしたと言う。「家族は皆、未明を尊敬し、画家の伯父、翻訳家の伯母など、親戚は本当に一同仲が良かったのです。大人数で家族旅行に行くこともありました。 また、後輩の文学者にも慕われていました。」
仕事ぶりについては「 午前中はこの書斎で執筆して、午後になると編集者や、若い作家、友人が訪ねて来ては接客でしょうか、近隣の蕎麦屋やラーメン屋、時折は新宿の『樽平』『秋田』という店に飲みに行くこともあったそうです。 特に同郷の作家・小田嶽夫とは親しかったようですね。 近くの中華屋で、チャーシューとビールで晩酌を楽しんでいた、とも聞きました。日本酒だと月桂冠を好んだようです。」
趣味だったマッチ箱のコレクションでも、高円寺駅、中野駅など近所の店はもちろん新宿、銀座の喫茶店なども多くあったことから行動的にいろいろな店に行っていたことも伺える。
「直江津と高田の間、春日山で育ったせいか、新鮮な魚が好きで、よく魚屋を覗いて良い魚があると、散歩帰りに買って帰ってきましたね。晩年は、『うおと』という魚屋から美味しいお刺身を毎日届けて貰っていたほどです。」
メジロ、ウグイスなどの野鳥に餌付けして、良い声で鳴くのを楽しんでいた。 庭木の手入なども好み、見事な蘭の花を咲かせては、その芳醇な香りが玄関まで届いたと言う。
小学生だった英晴さんにとっては、「言葉が早口で伝わり難いところもあったが、家族を大切に、人としての根本を大事にされ慈愛に溢れた、優しい思いやりのあるお爺さんでしたね。たまに肩をたたいてあげたのですが、ポロポロと涙をこぼしたことがあって記憶に残っています。」
「この家の庭に池があるのですが、守り神のような、大きな黒い蛙がいて可愛がっていました。未明が亡くなったその日に姿を見せたきり、突然いなくなってしまい、皆でどうしたのだろうと不思議がったものです。」童話作家らしいエピソードで話しをしめくくった。
没後五十年が過ぎ、現代までを受け継がれた住居だが、2014年9月に惜しまれながらも取り壊された。
<協力・出典・参考文献>
小川英晴さん
新潟県上越市市民環境部文化振興課
新潟県上越市高田図書館小川未明文学館
岡上鈴江著『父小川未明』新評論刊収録年譜
杉並の書斎を再現して公開
新潟県上越市の小川未明文学館では、2014年に9月に取り壊された丸ノ内線東高円寺駅ちかくの居宅の書斎部分を再現し一般公開している。
小川未明文学館では、小川未明の著作や関連書籍が多種にわたり配架され、年齢に関係なく小川未明の世界を楽しめる取り組みを実施している。
●小川未明文学館(上越市立高田図書館内)
新潟県上越市本城町8-30 電話:025-523-1083
小川未明 プロフィール
本名・小川健作。明治15年(1882年)新潟県上越市幸町生れ。
早稲田大学進学のため上京し、「未明」の名付け親坪内逍遥、作家ラフカディオ・ハーンに出会う。在学中の明治37年(1904年)9月、処女小説「漂浪児」を発表。好評を博し、翌明治38年(1905年)、早稲田大学を卒業。 翌年5月に未明は結婚、6月に早稲田文学社に入社『少年文庫』の編集に携わる。
童話雑誌『赤い鳥』創刊後は童話を中心に活動し44歳で童話専従を宣言した。一千編に及ぶ素晴らしい童話の数々を発表したが晩年を過ごした東高円寺の居宅で昭和36年(1961年)5月、脳出血で倒れ、79歳でこの世を去る。
DATA
- 最寄駅: 東高円寺(東京メトロ丸ノ内線)
- 取材:高遠 瑛
- 撮影:NPO法人TFF/高遠 瑛 協力:新潟県上越市文化振興課
- 掲載日:2014年11月16日
- 情報更新日:2018年10月01日