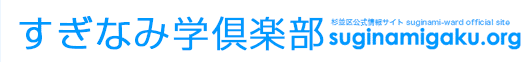- トップページ
- 文化・雑学
- 読書のススメ―杉並ゆかりの本
- 恍惚の人
恍惚の人
著:有吉佐和子 (新潮文庫)
会社勤めを終え、新高円寺駅から自宅に向かう途中、昭子は、雪のなか外套も着ず傘もささず、血相を変えて歩いてくる舅の茂造に出くわす。訳をたずねても、茂造の返事は要領を得ない。帰宅した昭子は、二世帯住宅で別居している姑が急死しているのを発見、さらに、茂造が妻の死も認識できない症状にいたっていることを知る。茂造が、息子で昭子の夫、信利には暴漢呼ばわり、郷里の新潟からかけつけた娘、京子も誰だかわからず、わかるのが、昭子と、孫で昭子と信利の一人息子、敏だけという事態に直面し、昭子は、茂造の介護は、誰でもない、それは私がやれることだという気持ちになっていく。
おすすめポイント
歴史・文化について、女性の視点から数々の名作を描いた有吉佐和子の社会派小説。五十歳を越えた有吉佐和子が、自らもやがて老いることを念頭に、当時住んでいた杉並を舞台に、認知症の舅と格闘する女性の姿を描いている。長く公にならなかった認知症の問題を正面から取り上げ、高齢化社会を迎えるにあたって充分に準備のできていなかった1970年代初頭、この作品は杉並から全国に大反響を巻き起こし、映画化、テレビドラマ化もされた。
梅里や松ノ木の敬老会館(当時)、茂造の徘徊先、青梅街道など、具体的な地名が随所に登場し、問題を身近かに感じさせられる。有吉佐和子ファンのみならず、老人問題についてあらためて考えたい方にも必読の書。
DATA
- 取材:井上直
- 掲載日:2012年05月31日