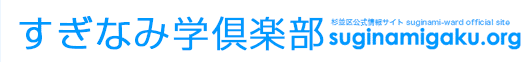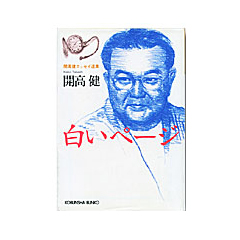- トップページ
- 文化・雑学
- 読書のススメ―杉並ゆかりの本
- 白いページ
白いページ
著:開高健 (光文社文庫)
小説家として、ベトナム、ビアフラ、アラスカ、アマゾン、モンゴル…、世界の戦場、秘境、また、日本国内を駆け巡り、体当たりで発言と行動、作品を発表しつづけ、コピーライターとしても、数々の名コピーを生み出した開高健さん、その本格的な創作活動は杉並で始まった。寿屋(現サントリー)の宣伝部の社員として一家で大阪から上京、下井草の社宅に住まい、1958年(昭和33年)、『裸の王様』で第38回芥川賞を受賞、その後、著述業に専念するため井草に転居、計19年余り、茅ヶ崎に移るまで、杉並が開高さんの生活の拠点だった。本書は、開口一番、そのあだなの通り、文学、政治から、釣り、食、酒、映画、旅の話題まで、豊穣多彩な開高さんの魅力満載のエッセイ集だが、杉並での日々を綴った作品も収録されており、開高さんの豪放で一方繊細な一面をのぞかせてくれる。
おすすめポイント
頑強で病気知らずの開高健さんがついに胆石でダウン、天沼の病院に入院した44歳の日々、ご近所さんで文壇の大先輩、釣りの師匠でもあった井伏鱒二さんとのエピソード、井草の自宅にこもり執筆に入るもはかどらず、外から漏れ聞こえる音で一日の変化を読み取っていた話など。「わが井荻界隈の夜の静寂は新しい疲労を知ったのだろうか…」(「聞く」より)。早朝に聞く音が、牛乳配達から新聞配達に変わり、近所の畑は減少し、変貌する杉並の様子に蕭然とする開高さん、杉並で暮らしたその姿をはっきりと彷彿させてくれる作品だ。
DATA
- 取材:井上直
- 掲載日:2013年04月11日