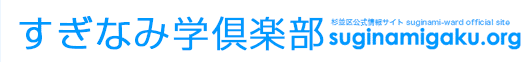- トップページ
- 文化・雑学
- 読書のススメ―杉並ゆかりの本
- 東京八景
東京八景
『東京八景』 著:太宰 治 (新潮文庫 『走れメロス』 に収録)
青森、津軽から上京、兄をたよって新宿、戸塚に下宿してから、杉並、天沼の下宿を引き払うまでの、戦前の八年余りを描いた、作者、太宰治の自伝的短編小説。
三十歳を越え、小説家として収入を得てどうにか暮らせるようになり、東京市を離れ三鷹村に所帯をもった主人公は、上京以来、初めて一息つくことができる。どうにかこの家を守っていきたいと妻に告げたとき、主人公に、印象に残る東京市の風景を八つに絞リ小説化する構想が生まれる。なけなしのお金を持って伊豆の安宿にむかい、支払いを疑われながらも落ち着いた先の部屋は、まるで、かつて暮らした杉並、天沼の下宿のよう。気を取り直して執筆にはいるが、思い起こすのは東京市の風景ではなく、そこにいた自分自身と人々の生活の姿ばかり。苦悶に満ちた日々が走馬灯のように甦る。
おすすめポイント
太宰治は、千葉、船橋時代をはさんで、二度、計四年余りを、杉並、天沼ですごした。一度目は郷里の先輩、飛島方(天沼3丁目)に下宿。二度目は、アパート昭山荘、碧雲荘(天沼1丁目)、下宿屋鎌滝方(天沼1丁目)と移り住んだ。小説の主人公の回想を通して、天沼での太宰治の多難な姿をうかがい知ることができる。当時の天沼、荻窪の風景や、どん底の太宰治を見放さなかった、文壇の先輩達、小説家仲間達も仮名でさりげなく登場。杉並での太宰治を知りたい方はもちろん、広く文学好きの方にも必読の書。
DATA
- 取材:井上直
- 掲載日:2012年01月19日