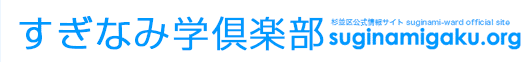- トップページ
- ゆかりの人々
- 著名人に聞く 私と杉並
- 山下洋輔さん
山下洋輔さん
山下さんとジャズ
――山下さんにとってジャズとはどんな音楽ですか?
自分の分身のようなものなんですが。あえて音楽的なことで言えば、やっぱり「即興の音楽」かな。人間には即興を楽しむ精神というのがあると思うんです。その場でこの人はこういうことを作っている。見ている前でどんどんできていく。それを面白がる。ジャズでは同じ素材(楽曲)を使ってある人はこうやった、次に出てきた人はまた別のことをやった、それを楽しむという大きな要素があります。それから忘れてならないのは、アフリカとヨーロッパがアメリカ新大陸で出会って生まれたというジャズの壮大な歴史的背景ですね。その痕跡が音にもリズムにも残っています。それを聴き取るのもとても大事なことです。
――即興で積み重ねていくセッションは、いわば対話のようなものですね。
皆が知っている曲をまずやるわけですが、即興のパートになったら、ソロをとる人がその場で音を作っていく。共演者はそれを聴き取って「こいつは今日はこういうことを言いそうだな」などと考えたり(笑)。リズムセクション(ドラム、ベース、ピアノ)とその他の楽器の対話も必要だし、リズムセクションのなかでお互いが聴きあって対話をします。相手の出す音に自分の音をぶつけたり合わせたりして演奏が進むんですね。
自分の音 とは
――「自分の音」とはどうやって作るのですか?
これは全ての音楽家の究極の目的ですけど、今、セッションで言っている自分の音というのは、ピアノならピアノの役割と言ってももいいかもしれません。ある時は伴奏をしてある時はソロをとる。ピアノという楽器だから一人だけのソロコンサートもあるかもしれない。その時に出す「自分の音」というのはつまり自分の音楽ということですね。あらゆる音楽の知識と技術を習得して、それを全部つかって自分を表現できれば理想でしょうね。まずはそれまでの知識や技術をおぼえて、それから自分の個性を出していくというのはどんな分野でも同じ修行ですよね。ジャズでは即興演奏の中に自分でなければ出せない音が表現された時に「自分の音」ということになるんでしょうね。
――その「自分の音」をもとに即興演奏を行うのですね。
即興のやり方ですが、普通は、曲についている和音、コードネームを頼りに、そのコードの和音に合うような音を自分で作っていくんです。クラシックでいうと「変奏曲」ですね。モーツァルトの「きらきら星変奏曲」がありますが、最初は単純なメロディだったのが、どんどん変奏して最後は大変なことになっちゃう(笑)。ジャズはまさにそれをやっているんです。モーツァルトも、あの曲は即興で作ったんじゃないかな。バッハも、王様から音を渡されてその場で演奏したというし、ベートーベンに至っては、即興演奏大会で相手を打ち負かしたっていう話も残っているくらいです。同じテーマで変奏し合って、この人はこうやった、あの人はこんな風にしたという、その楽しみ方を現代に残しているのはジャズだけなんですね。だからこそ、それをわかってしまうともう離れられなくなる魅力的な音楽なんです。
ジャズストリートへの思い
――1997(平成9年)からほぼ毎年ジャズストリートに参加されていますが、今年はどんなステージになるのですか。
以前から親交のある、和太鼓演奏の「鼓童」という集団がありますが、そこから最近独立した金子竜太郎さんをお招きして、和太鼓対ピアノの「決闘」をやります(笑)。今年は杉並第一小学校の特設ステージでやりますが、日本の和太鼓の多様性というか、なぜこれがジャズに通じるのかという意味で、すごく面白いことができると思います。竜太郎さんがどうくるかですね(笑)。あくまでも伝統的なたたき方をしてくるのか、変貌していきなりジャズのテクニックでやってくるかもしれない。それは当日までわからない。まさに即興の「対話」ですから、楽しみにしていてください。
――これまではずっと神明宮の神楽殿で演奏されていたのですよね。
これも阿佐谷のご縁でね。阿佐谷北6丁目に実家があるんですが、父親が亡くなったときに、神明宮の神主さんに葬儀をしていただいたんです。その頃ちょうどジャズストリートが始まっていて、「こんなイベントがあります。氏子さんとして協力されませんか」という風に、神主さん経由で橋渡しをしていただいた。それで、父親の葬儀ということがきっかけでもあったので、なんとなくこれは何か恩返しをという気持になって、それはいいですねってこちらから積極的に参加することになったんです。そうすると、神明宮でやるなら神楽殿にピアノを上げますということで、かがり火まで焚いたステージができあがりました。薪能の世界にグランドピアノがあるという光景で、これはもう他では絶対味わえませんね。
――これまでもたくさんのユニークな場所で演奏されていますが、お神楽殿で演奏されるというのは何か特別な感じがあるのですか。
ありますね。かがり火という原始の時代から人間の情念をかき立てるような状況があるせいか、神社の中で神様に音を捧げているような気持になりますね。まさに奉納ですね。音楽っていうのは、もともとは超越的なものにつながろうとしたのが始まりかもしれませんよね。祝詞もそうですが、踊りにしろ歌にしろ、そういうものによって人間を超えた存在に訴えかけているのかもしれない。それが実感としてわかるようなステージですね。
――ジャズストリートでは、いつもご自身が注目されている若手演奏家と共演されていますね。
最初はソロでやりました。もちろん楽しいんですけど、お祭りなんだからだれか相棒を連れてきて一緒にやりたいというのが始まりですね。せっかくの機会だから初めて人前でやるような若い人を連れてきて、紹介したいと思ったんです。ちょうどそのころには洗足音大や国立音大でジャズを教えていて、いろいろな才能のある若い人に出会っていたので、そういう人たちを世の中に紹介したいと、そういう動機とも重なっています。もちろん新人だけじゃなくて、ベテランにもきてもらいますが、大体若手の紹介ということでは一貫していますね。
音楽活動における信念は?
――現在の音楽活動をされるうえでの信念はどのようなものですか。
音楽をやっている瞬間は、すべて一滴もあまさず自分を表現してしまいたいと思っています。そうしなければ終われない、そういう心構えがいつもありますね。その場で音を作っていますから、何か「よし!」っていう瞬間を捉えない限り、やめられない。それは、曲の長さに関係なく、感覚としてこれで悔いなく表現できた感じる瞬間が大事だということですね。
――そこまで出し尽くして、新たなエネルギーは一体どこから補給するのですか。
補給されているのかどうか(笑)。でももうそういう体質になっちゃっているみたいですね。たとえば、1年がかりの大仕事で、全部やりつくしてもぬけの殻になったはずなんだけど、「全部出し切ったからこそ、あらためて外から新しいものが入ってこられる。真空ではいられないから、そこにまたばーっと何かが入ってくる。もぬけの殻になればなるほどまたすぐに別のもので満たされる」と、こういう楽観的理論をあみだして(笑)、なんとかやっているんですけどね。
――音楽以外の分野でも次々と新しい試みをされていますね。
ジャズをやることによって培った自分の感性やものの考え方を、新しく体験する全てのものに応用しているような感じですね。文章を書くのも、絵本を作るのも、自分にできるのはジャズで得たものを叩き込むしかないという気持で取り組んでいます。昔から、できないからやめますとはいえない性格で、やって失敗しても経験はしとくべきだって考えて、新しい分野に挑戦してきました。それが今につながっているんだと思います。
山下洋輔 プロフィール
1942年、東京生まれ。ジャズ・ピアニスト。1969年、山下洋輔トリオを結成、フリー・フォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。内外の一流ジャズ・アーティストとはもとより、和太鼓やオーケストラとの共演など活動の幅を広げ、1999年に芸術選奨文部大臣賞(大衆芸能部門)、2003年には紫綬褒章を受章。2008年1月、佐渡裕指揮の東京フィルハーモニー交響楽団と「ピアノ協奏曲第3番<エクスプローラー>」発表。3月ニューヨーク・トリオ結成20周年記念アルバム『トリプル・キャッツ』リリース。母校国立音楽大学招聘教授、名古屋芸術大学の客員教授を務める。多数の著書を持つエッセイストとしても有名。
DATA
- 取材:ヨシダ
- 掲載日:2009年10月10日