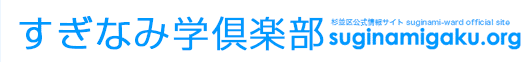- トップページ
- 歴史
- 道具に見る昭和の暮らし
- 裁縫箱
裁縫箱
戦争の足音が聞こえてきた頃の裁縫の思い出
お裁縫のはじめの記憶として残っているのは、6歳のころですから、昭和16年~17年くらいでしょうか。空襲はまだ始まっていませんでしたが、男の人たちは、兵隊さんになって出て行く時代でした。
うちの父は長男だったので、戦争には行きませんでしたが、結婚をして分家をした叔父が出征していきました。気の毒なのはひとり残された若いお嫁さんで、夜が怖いし、寂しいと言うんですね。
ですから、わたしの祖母(嫁からみたら姑にあたる人)が、夕飯を食べてから寝る前のひとときに、叔父の家に出かけていって、着物を縫ったり、繕い物をしたりしながら、お嫁さんの話相手をしていました。そんなときは、わたしたち孫も一緒についていって、祖母のために、針の糸通しを手伝いました。
針仕事で忙しかった女性たち
当時は、子どもは洋服でしたが、母は一日中着物でした。父は会社へ行くときは背広ですが、帰ると和服に着替えていました。
そういった家族の衣類は、父の背広をのぞいて、ほとんど母と祖母が縫っていました。着古して裾や膝が傷んだ着物は、一度ほどいて、天地をひっくり返して縫い直していました。傷んでいる部分を「おはしょり」の中に隠れるように縫い直せば、また長く着られます。
そんな風に昔は、一枚の布を大事に使っていました。季節ごとに、布団の皮の縫い直しもしていたので、母も祖母も、手を休める暇がなかったと思います。母たちが使っていた裁縫箱は、ひきだしがたくさんあって、針や糸、指貫、ヘラ、鋏などがつまっていました。袖型といって、たもとの丸みをつけるために、角が袖の形に丸くなっている板もありました。
また、くけ棒といって、和裁をするときに、布がたるまないように端を挟んで張る棒もついていました。今は博物館でしか見ることがなくなってしまいましたが、昔は本当にどこの家にもありました。
わたしの記憶の中では、母が裁縫をするのは、たいてい、子どもたちを寝かせつけた後。正月の晴れ着用の生地をデパートで買ってもらい、母に縫ってもらったときの嬉しさは格別でした。
ミシンの登場によって変化した裁縫箱
戦争が終わって、わたしは都立高校に入学しました。進学コースだったので、家庭科はあったのかどうか、記憶にありません。もともと裁縫があまり好きではなかったので、それをいいことに練習もせず、嫁入り前の娘としては落第だったと思います。けれども、母はうるさく説教したりしませんでした。しなかったというより、「戦争が終わって今は時代が違うから」と思うと言えなかったのだと思います。
妹はミシンが好きで、「装苑」や「ドレスメーキング」といった雑誌を一生懸命読んでいました。新婚旅行のときに着ていったコートは妹が作ってくれたものです。
女性の興味は洋裁へ移っていきましたから、昔ながらの裁縫箱はすっかり陰が薄くなりました。嫁入り道具に持っていった裁縫箱は、セルロイドの箱でした。和裁道具が消えたかわりに、チャコペンやミシンのボビンといった洋裁の道具が入るようになりました。
また、当時は針山を手作りする人が多く、わたしは目の詰んだ布にヌカをいれて使っていました。髪の毛を入れたり、綿を入れて使っていた人もいたようです。ただ、そんなことも、店で針山が安く買えるようになると自然としなくなりました。
生活のための裁縫から解放されて
その後、大量生産時代に突入すると、裁縫をしなくても、生活に困ることはなくなりました。
結婚してから一生懸命にした針仕事といえば、赤ん坊のオムツくらいです。大姑から、新しいサラシよりも使い古しの浴衣のほうが赤ちゃんの肌にいいと言われて、浴衣をほどいて縫いました。
その大姑は、自分の古い着物をほどいては、腰紐をせっせと縫っているような人でした。姑が里帰りに行くときには、「90のおばあさんが縫った紐だから、目出度いと思って持っていってちょうだい」と何本も持たせていました。時代が変わっているにもかかわらず、死ぬまで針を手放さなかった明治の女性で、今考えても本当に芯が強かったなあと思います。
裁縫嫌いのわたしが言うのもおかしいですが、そういうおばあさんが少なくなったのは、ちょっと寂しい気がします。
DATA
- 取材:河合 美千代
- 掲載日:2006年04月24日