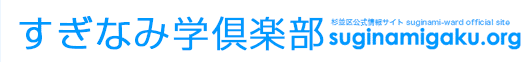- トップページ
- 文化・雑学
- 読書のススメ―杉並ゆかりの本
- 水声(すいせい)
水声(すいせい)
著:川上弘美(文春文庫)
芥川賞作家の川上弘美さんが描く、ある女性とその家族の秘められた人生の物語。1996(平成8)年、主人公の都(みやこ)は、弟の陵(りょう)と共に、ママの死後10年ぶりに杉並の生家に戻る。古屋の庭から漂う草の匂いが彼女の記憶を呼び覚まし、夢の中で再会したママに導かれるように、彼女は過去をさまよい、家族の物語を語り始める。
全編を通して、都の影のように登場するのが、50歳の若さで逝った最愛のママだ。成長するにつれ、変化していく陵への感情に戸惑う都に秘密があるように、ママも人知れぬ秘密を抱えていた。都は、自分の過去と、ママの秘めたる心境に思いを巡らし、自らが選択した生き方を受け入れる境地に達する。その心の軌跡が静けさをたたえた筆致で描かれ、読後に深い味わいを残してくれる。日常の中に幻想が顔をのぞかせるのが持ち味の、川上作品の世界観に触れることのできる作品だ。
おすすめポイント
川上さんは、1958(昭和33)年生まれ。3歳から杉並区の高井戸に暮らし、学生時代をほぼ杉並で過ごした。都は、作者と同じ年に生まれ、高井戸付近と推測される場所で育っている。彼女が回想する、親友の奈緒子と陵と過ごした夏の日々のみずみずしい描写には、作者自身の体験とふるさとである高井戸への愛着が投影されているようだ。読者を、空き地が残り、のんびりした空気が漂う往時の高井戸付近にいざなってくれる。
3人が、片側3車線に拡幅工事中の環状8号線を眺め、炭酸飲料水を飲んで夏の午後を過ごす場面は、短いながら印象に残る。アスファルト上のかげろうや、にわか雨の後の湿気を帯びた空気など、五感を通した記憶が、高度経済成長の象徴のような環状8号線と交錯し、ノスタルジーの中に変わりゆく時代が描き出され秀逸だ。
DATA
- 取材:村田理恵
- 撮影:村田理恵
写真提供:杉並区広報課 - 掲載日:2024年04月29日