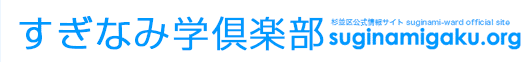藤沢昌子さん
書との出会い
筆を持ち始めたきっかけは何ですか。
もともと、花嫁修業の一環として書を始めたことが発端でした。当時は19歳でしたね。
この道に進んだ転機はありましたか。
20代前半頃に京都の大覚寺練成会で生まれて初めて『かな』の世界に明確に触れたんですね。そこで一気に『かな』の世界にのめりこみました。
先生のお手本がない作品づくりを創作と言うのですが、創作をやってみたことで、自分の字を書くことの面白さに心が非常に強く動きました。書は熱心に練習していたのですが、創作するスタイルに目覚めて以来、それがきっかけとなってさらに力を入れて稽古に励むようになりました。
創作というのは自らの字を書く、ということですから、先生のお手本通りに書かない。そのため、次第に先生からは相手にされなくなっていったんですね。・・・今思うと、可愛くない生徒だったかもしれない(苦笑)。ただ、創作にまつわる指導は先生から特に頂くことがなかったので、先生の下を離れるということを決心するに至りました。
作品を作り出す作家として、書家として生きていきたい
先生の元を離れて、その後は?
書の世界で登竜門的存在の大東書道(1969年に創刊された大東文化大学で刊行される唯一の競書)という雑誌があるんです。そこへ自分の創作した作品を投稿してみたんですね。自分の実力はどれくらいあるんだろう?って。確かめたかったんです。
そしたら私の作品は毎回必ず掲載されて、評論がついていたんです。それを何度も繰り返して、そうして掲載され続けていくことを見ていきながら、自分の作品に対する自信を深めていきました。様々な試行錯誤を経て、私自身の教室を開くことを決意するに至ったのです。
単独で道を開くのは大変なことですよね。先生を書の道に駆り立てた、その動機は何でしたか?
書の道を歩みたかった、ただそれだけです。とにかく夢に向かって、前に進んでいきました。作品を作り出す作家として、書家として生きていきたい、そう思ったんです。母もそんな私を見て応援し、支えてくれました。
書だけで生きていく、というのはなかなか困難なことが多々あるんですね。教室のほかにも生活のためにアルバイトなどもしました。またさらには私自身の精進ということもあり、その一方で稽古も続けていきました。
初めて題字デビューしたのは、NHK銀河テレビ小説の作品です。NHKのディレクターに声をかけられました。また、周囲から個展を勧められ、30歳で好きな詩人である中原中也の個展を荻窪の画廊で開きました。それが朝日新聞で紹介されたものですから、画廊に多くの人が集まり、以後、新宿(紀伊国屋画廊)、銀座(渋谷画廊、文藝春秋画廊、鳩居堂など)での個展を開催させて頂きました。
書家としての人生
現在も書の教室を主宰していらっしゃいますが、いま振り返って、藤沢先生にとって書はどんな存在でしょうか。
人間というのは、好きなことに関して努力を惜しまないものだとも思うんですね。私は、書家の篠田桃紅さんに憧れたんです。師もなく弟子もなく、作家として生き、一人で活動している方で、私も一人でやってみたい、と思って取り組んできました。
今思うと、書は私にとって天職だったと思います。昔はその質問をされると、命を保つために与えられた仕事かしら、と答えました。でも今、60歳を過ぎて、気力や体力の衰えを感じる年齢になって振り返る時に、若い頃にわき目も振らずにやってきた、私にとって輝くものであった『書』というのがが、幻であり夢のような気がします。
もちろんこの世界に終わりはなく、私自身は支障が出るまでやり続けるでしょうけれど、私たちはやがて天に召されていく存在ですよね。そう思うと、人の命のなんとはかないことかと思うんです。志半ば以前ぐらいでしょうか。
インタビュー後、京都の大覚寺練成会でかいだ紙の匂いが今でも忘れられない、と語った藤沢氏。
「まるで白粉のような紙の匂いと、寝る間も惜しんで励んだ稽古と、全てがからまったあの時のことは今でも強烈な印象」と目を細めた。
藤沢氏の書は、現在、美術年鑑にも登録されている。
藤沢昌子 プロフィール
書家。昭和20年9月、長野県生まれ。杉並区在住。
コミュニティクラブたまがわ(東京・玉川高島屋)講師。個展は昭和50年に「中也と詩う」を発表して以来、紀伊国屋画廊、文藝春秋画廊、鳩居堂画廊、あきるの市燈々庵ギャラリー、埼玉伝統工芸会館などで開催、またNHK『御宿かわせみ』を初めとする各局テレビドラマの題字、東宝・松竹など舞台作品の題字の揮毫、ロゴ制作など幅広く活躍中。主な著書「毛筆による手紙の書き方」(平凡社)、「万葉秀歌相聞」「百人一首」(審美社)、「えんぴつと筆で詠う与謝野晶子」(双葉社)
DATA
- 最寄駅: 浜田山(京王井の頭線)
- 取材:桜子
- 撮影:昌の会
- 掲載日:2009年07月23日
- 情報更新日:2016年03月24日