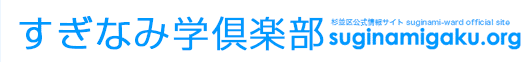都市農業のいまと取組み
50人いたら50通りのやり方がある
荻窪駅周辺の繁華街を抜け、閑静な住宅地を歩いていると、ふと空が広くなる場所がある--井口幹英さんの畑だ。
夜には、防蛾灯がほんのりと緑色に周囲を照らし、蛾の食害を防ぐだけでなく、地域の防犯の役割も果たしている。
井口さんの畑では、防蛾灯のほかにも、防虫ネットを取り入れるなどして、無農薬有機栽培を実践している。
「味が良くて病気に強い種を選び、畑を上手にローテーションさせることで、連作障害だけでなく、土壌消毒などで余計な薬剤を使用することを回避しています」
井口さんの畑は、江戸時代中期から始まり、幹英さんで11代目。無農薬有機栽培を始めたのは、先代からだ。
「1年に1度、作付前の畑に堆肥を投入し土をぼう軟にして、同時に保水性・排水性の向上を計ります。また、土が酸化するのを防ぎ、有用微生物の住処にもなるので、土に粉炭も混ぜています」
畑に関する本の所蔵は、50冊以上。今でもときどき買って勉強を続けているという井口さん。
「おいしい野菜をつくるということは、どれだけいい環境を作ってやれるかということです。ただし、50人いれば50通りのやり方があります。ひとつとして同じ畑はありません。土壌の性質も違えば、風の抜け方も陽の当たり方も違います。良いと言われていることを実践するとしても、自分の畑に合うように応用していかなければならないんです」
さらに、良い味と良い根が出るように秘伝のボカシ肥を使うなど、井口さんの畑には、おいしい野菜を作るためのさまざまな工夫が凝らされている。
写真:井口幹英さんの畑
素材の味+αのおいしさを伝えたい
井口さんは、栽培した野菜の9割を、畑の前で対面販売をしている。
「育てた野菜が一番おいしい瞬間を逃さずに販売したいんです」
幹英さんが、家業を継ぐために就農したのは、いまから12年前の29歳のとき。大学卒業後は、自動車販売のディーラーとして働いていた。
「自分が持っている商品知識や+αの情報が、購入いただくお客様の満足度を上げる--それは自動車でも野菜でも同じだと思うんです」
就農後しばらくして日本ベジタブル&フルーツマイスター協会(現 一般社団法人日本野菜ソムリエ協会)で、野菜ソムリエの資格を取得。それぞれの野菜の特徴、保存や料理の仕方などを学び、お客様によりよく伝えられるように努めている。
直売所:「井口ミニファーム」東京都杉並区清水1-31-14
営業時間:不定期 【夏季】16時ごろ~ 【冬季】14時ごろ~
伝統大蔵大根に歴史的なお里帰りをさせたい
井口さんが、今年(2012年)新たに挑戦しているのが、江戸東京野菜の伝統大蔵大根の栽培だ。現在、世田谷区の特産品として栽培が盛んになりつつある伝統大蔵大根だが、ルーツは意外にも杉並区にある。
伝統大蔵大根は、秋つまり大根と呼ばれる品種だ。秋つまり大根は、江戸時代に、豊多摩郡(現在の杉並区が含まれる)の百姓・源内が作りだした「源内つまり大根」がはじまりとされている。それが、世田谷区の大蔵原に伝わって、伝統大蔵大根となった。
「もともと『冬どり大蔵』というF1種を育ててきたので、伝統大蔵大根のルーツを聞いて、ぜひ歴史的なお里帰りをさせたいと思いました」
スーパーなどで多く出回ってるのは、青首大根がほとんどだ。白首の大蔵大根は、水分が少なく、煮物にしても煮くずれしにくく、味も良い。井口さんの畑でも人気商品のひとつだ。
「今年はまだチャレンジなので、商品として店頭に出せるかどうかはわかりませんが、12月ごろには収穫する予定です」
伝統大蔵大根のお里帰りには、「さざんか天沼教室」の中学生もサポーターとして参加する。
「9年前から『さざんか天沼教室』の生徒といっしょに野菜を育てています。1学期は、うちの畑のお手伝いをしてもらって、2学期は自分たちで冬野菜を育てるのが主な活動。終業式には、畑でBBQをしたり、収穫した野菜でこだわりのベジタブルちゃんこ鍋をしたりもしています」
杉並区は、少量多品目でバラエティ豊かな野菜作りが行なわれているが、特産品は少ない。伝統大蔵大根のお里帰りを期に、区内のブランド野菜が誕生する可能性もある。
応援してくれる人をひとりでも増やしたい
区内の生産緑地は、20年後には現在の3分の1くらいになってしまうだろうと試算されている。井口さんの畑も、区内で指定されている生産緑地のひとつだ。
「井口家も昭和40年代の高度成長期の頃から、農業と不動産業の二足のわらじを履いています。都市農業を続けていくには、やはり不動産での収入がなければやっていけないのが実状です」
都市農業の後継者たちを苦しめているのが、相続税の問題だ。相続が発生してから10ヶ月以内という短期間で高額の税金を納めなければならず、多くの後継者たちは、更地で売りやすい畑を手放してしまう。
「都市に緑地を残すことは、大きな意味があります。畑であれば、地域の方に新鮮な野菜を提供することができるし、また災害時には、避難所や仮設住宅をつくることも可能です」
景観の問題だけでなく、防災といった視点でも都市農業の「多面的機能」が発揮されるのは明らかだ。
「もちろん、私たちもただ手をこまねいているだけではありません。しかし、現実には法改正をするなどといった大きな変革が必要です。さまざまなメディアを通じて、都市農業の現実を知ってもらって、一人でも多くの方が応援してくれることを願っています」
DATA
- 取材:佐竹未希
- 掲載日:2012年10月25日
- 情報更新日:2019年02月26日